建具職人とは、家の中の引き戸やドア、ふすま、障子など、開け閉めする“境界”をつくる専門職です。ただ木を切って組み立てるだけの仕事と思われがちですが、実際には「動き」「納まり」「見た目」のすべてがそろって、ようやく一人前の仕事になります。たとえば、ほんの1ミリでもズレがあると、開閉時に引っかかったり、建具がゆがんでしまったりします。こうした不具合を防ぐためには、材料の性質を理解し、わずかな誤差も見逃さない精度が求められます。
また、最近では既製品だけでなく、リフォームや注文住宅に合わせた“オーダーメイドの建具”も増えています。現場で寸法を測り、空間や使う人の暮らしに合わせて調整する。そうした繊細な手仕事が求められるのが、建具職人の仕事です。一見地味に見えるかもしれませんが、その仕上がり一つで、住まい全体の質感や使いやすさが左右される仕事だと言えるでしょう。
正社員・請負・弟子入り。求人形態で何が変わる?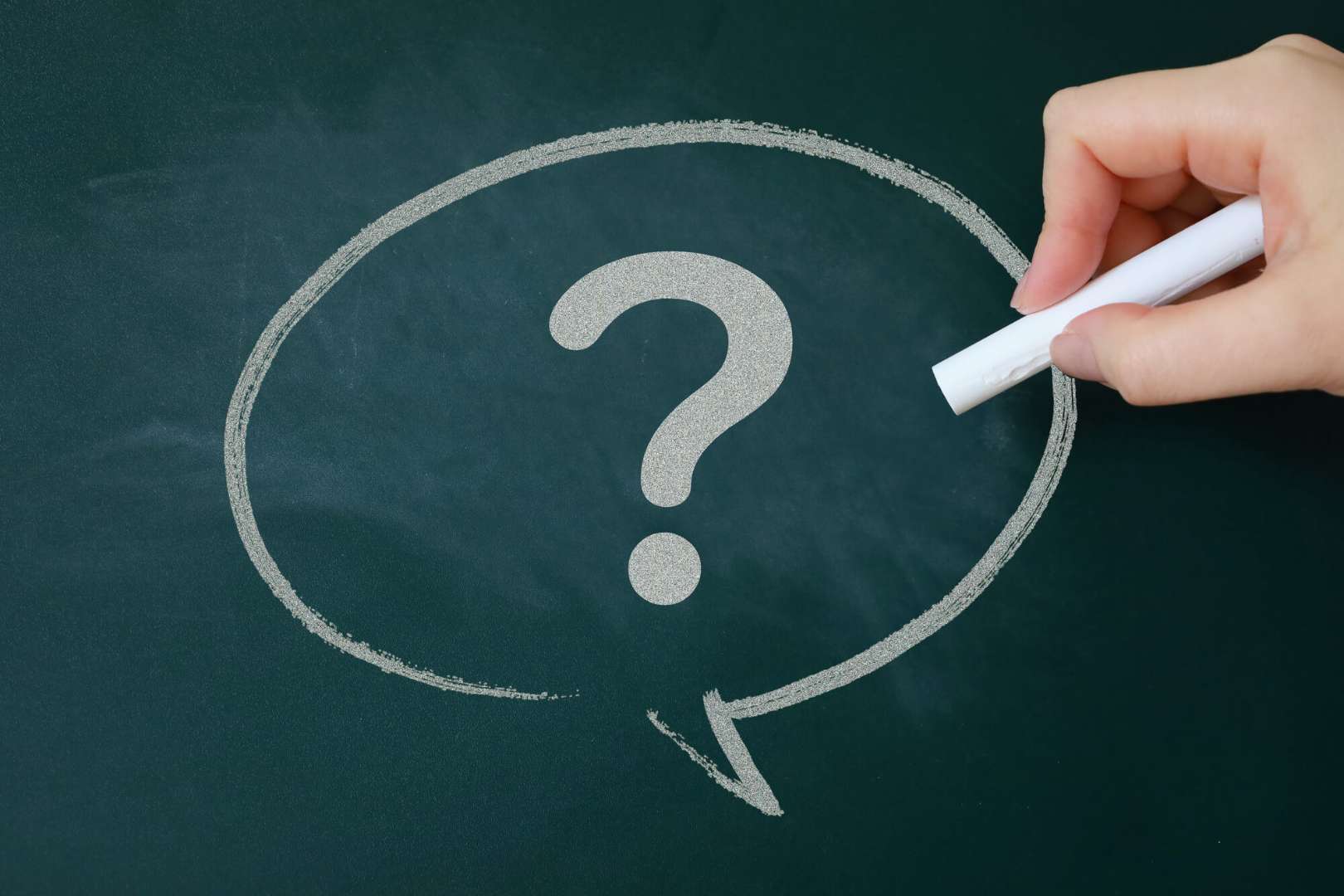
建具職人の求人には、いくつかの雇用スタイルがあります。最も多いのは正社員としての募集です。企業に雇われて、現場に出て、製作や取付を担当する働き方です。社会保険や手当が整っている場合も多く、安定して働きたい人に向いています。一方、経験を積んだ職人になると、請負契約で仕事を受けることもあります。この場合、報酬は歩合制に近く、実力次第で収入が増える一方で、仕事の段取りや請求業務なども自分でこなす必要があります。
もう一つ、いわゆる“弟子入り”に近い形で、経験ゼロから現場で学びながら働く求人も見られます。こうした求人は、技術を一から学びたい人にとっては貴重な入り口ですが、待遇が不明確な場合もあるため、就業前の確認がとても重要です。
また、給与水準についても地域や会社によって差があります。都心部では仕事量が多い分、給与も比較的高い傾向がありますが、その分スピードや技術への要求も高くなります。逆に地方では、地域に根差した施工や丁寧な仕事が重視されることが多く、給与は控えめでも安定した環境が得られる場合もあります。
自分の経験値や希望する働き方に合わせて、求人の条件をよく見比べることが、後悔のない選択につながります。
求人票だけじゃわからない、現場のリアルを見抜く視点
建具職人の仕事は、現場ごとにやることも働き方も違います。だからこそ、求人票に書かれている条件だけを見て応募してしまうと、「思っていたのと違った」というギャップに悩まされることもあります。たとえば、「未経験歓迎」と書かれていても、実際は経験者がほとんどで新人が育ちにくい職場だった、というケースもあります。また、「手に職がつく」とあっても、具体的にどんな教育体制があるのかが書かれていなければ、入社後に自力で技術を身につけなければならないかもしれません。
こうしたギャップを防ぐために重要なのが、「現場見学の可否」や「社員の年齢層・在籍年数」といった、実際の雰囲気を示す情報です。質問しづらいかもしれませんが、面接の際に「入社後の研修やサポート体制」「若手社員の定着状況」「先輩の指導スタイル」などを具体的に尋ねることで、自分に合うかどうかの判断がしやすくなります。
また、職場の“空気”は言葉だけでは伝わりません。社員同士の距離感や、現場の整理整頓の状態、道具の扱い方など、見てわかる情報こそがリアルです。できれば事前に見学を申し出て、自分の目で確かめておくことをおすすめします。
経験ゼロから建具職人へ。3年で一人前になるために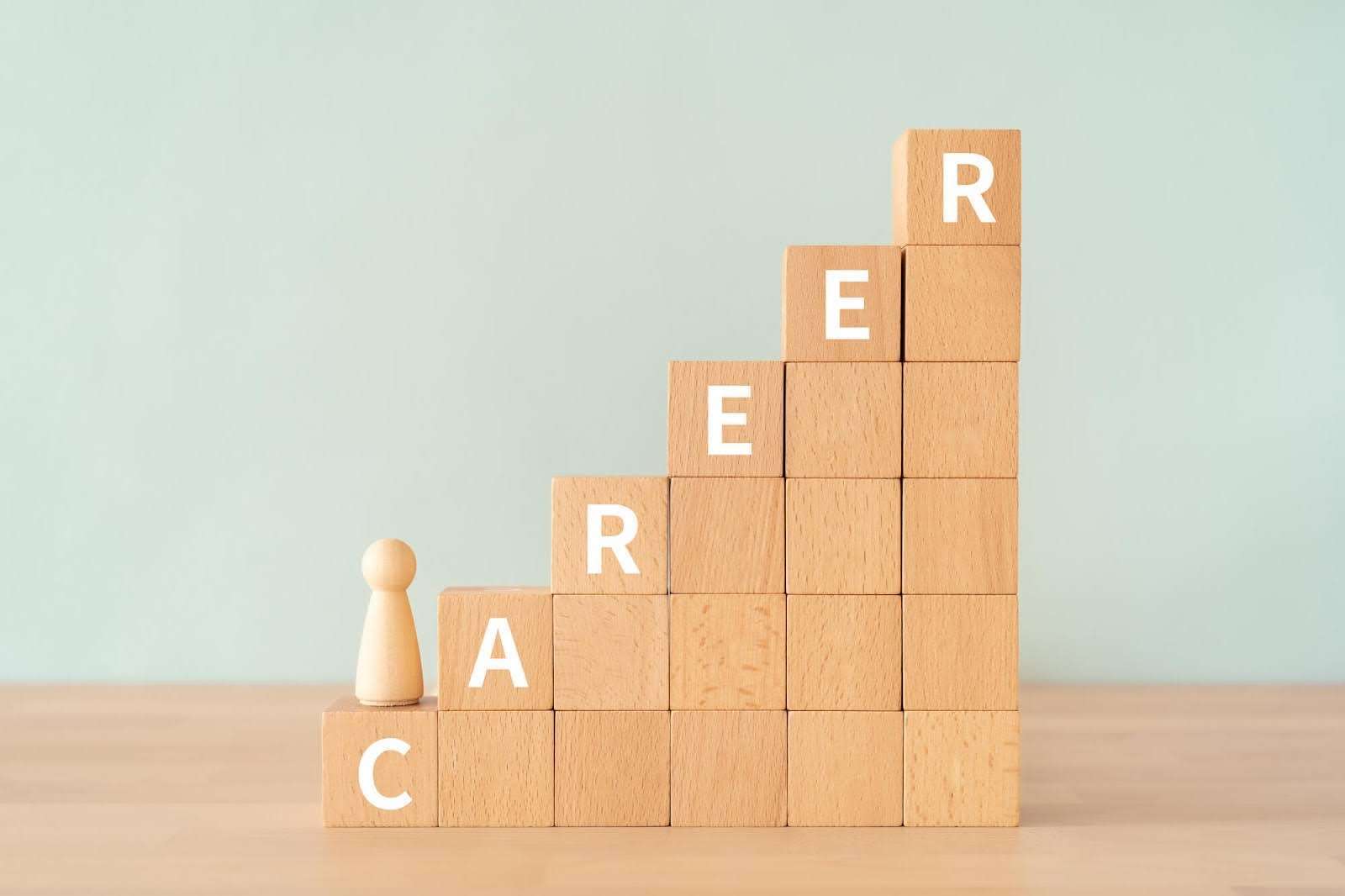
未経験から建具職人を目指す場合、いきなり難しい作業を任されることはありません。最初は、材料の運搬や簡単な下処理、掃除など、現場に慣れることからスタートします。こうした作業の中で、木材の種類や寸法の測り方、工具の扱い方を少しずつ覚えていくのが一般的です。1年目は、仕事の流れを理解し、職人としての基本的な姿勢や安全意識を身につけることが中心になります。
2年目以降になると、組み立てや取り付けといった実作業を少しずつ任されるようになります。ベテラン職人の手元で、実際に建具を作る工程を見て、真似て、何度も繰り返す。そうした実地経験を通じて、技術が身体に染み込んでいきます。この時期は、うまくいかないことも多く、つまずきを重ねる時期でもあります。しかし、それが確かな力に変わる過程だと考えることが大切です。
3年目になる頃には、図面を見ながら自分で段取りを組み、比較的簡単な建具であれば一通り任されるようになる人もいます。このタイミングで「建具製作技能士2級」の取得を目指すことも一つの目標になります。企業によっては、資格取得に向けた講習費の補助や試験日程の調整をしてくれるところもあります。自社育成に力を入れている会社であれば、そうした支援制度も整っているケースが多く、成長を後押ししてくれる環境が整っています。
「地元で手に職」は甘くない。でも誇れる仕事になる
都心の大規模現場とは違い、地元密着型の建具工事は、一人ひとりの職人が“顔が見える仕事”を求められる場面が多くなります。たとえば、住宅の建具やリフォーム工事では、お施主さんと直接やりとりすることもあり、技術だけでなく丁寧な対応や柔らかい人柄が評価につながることもあります。こうした地域の仕事では、短期的な利益よりも「この人にまた頼みたい」と思ってもらえる信頼の積み重ねが何より大切です。
カネコ建装のように地域に根差した企業では、流れ作業ではなく、現場ごとに異なる条件に合わせて“どう納めるか”を職人自ら考える場面が多くあります。そのぶん難しさもありますが、完成した建具が家族の暮らしに長く寄り添っていくという実感は、量産型の現場では得られないやりがいにもなります。もちろん、最初からすべてが思い通りにいくわけではありません。細かい調整や取り付けの工夫、現場ごとの癖など、職人としての引き出しが試される場面も多くあります。
それでも、少しずつ技術を身につけ、信頼されるようになっていく実感は、数字では測れない充実感を与えてくれます。「地元で手に職をつける」という言葉は簡単ですが、その裏には積み重ねと責任が必要です。だからこそ、自分の仕事に胸を張れるようになったとき、その意味がはっきりと見えてくるはずです。
カネコ建装では、こうした地域密着の仕事に共感し、手仕事の技術を磨きたい方を歓迎しています:
https://www.kanekokenso.jp/aboutus
「どこで働くか」が未来を決める。まずは比較と見学から
建具職人として長く続けていくには、最初に選ぶ職場がとても重要です。仕事内容や給与だけでなく、どんな人たちと一緒に働くのか、どんなふうに技術を教えてくれるのか。そうした環境の違いが、日々の積み重ねに大きく影響します。求人票には良いことしか書かれていない場合も多いため、自分の目で確かめる姿勢が大切です。
少しでも興味を持った会社があれば、面接の前に職場見学を申し出てみるのも一つの方法です。現場の雰囲気や職人同士の距離感、作業場の整頓状態など、短時間でも気づけることはたくさんあります。また、「未経験者がどのように育っているか」や「入社後の流れ」について具体的に聞くことで、働くイメージがはっきりします。
焦って応募するよりも、いくつかの会社を見比べ、自分に合った働き方を考える。そのプロセスが、職人としての良いスタートにつながります。
もし気になることや、詳しく知りたい点があれば、こちらからお気軽にご相談いただけます:


