「建具業界は、これから先どうなんだろう」「もしかして、あまり将来性はないんじゃないか?」
もしあなたが建具業界への一歩を考えたとき、そんな声を耳にして不安になっているかもしれません。「やめとけ」なんて言葉を見かけると、自分の選択が本当に正しいのか、迷ってしまいますよね。
確かに、そうした声が生まれるのには理由があります。その一つが、新しい家を建てる数、いわゆる「新築住宅着工戸数」が少しずつ減っているという事実です。人口が減っていく中で、これは避けられない流れかもしれません。この数字だけを見ると、「業界全体がしぼんでいくのでは」と感じてしまうのも無理はないでしょう。
しかし、それは物語の半分でしかありません。
新しい家が減る一方で、今ある家を「もっと快適に、もっと安全に、もっと長く使いたい」と考える人は確実に増えています。暮らしの中心にある住まいを見直し、リフォームやリノベーションをすることは、もはや特別なことではなくなりました。
そして、そのリフォーム需要の真ん中にあるのが、ドアや窓、間仕切りといった「建具」なのです。冬の寒さを和らげるための断熱ドアへの交換や、静かな暮らしを守る防音サッシの設置など、建具の役割はかつてないほど重要になっています。
「未来が暗い」とひとくくりにするのではなく、業界の中で静かに、しかし確実に起きている「変化」に目を向けること。そこには、これからの時代だからこその、大きな可能性が眠っているのかもしれません。
【光と影】建具業界の動向を左右する3つの大きな潮流

建具業界の今と未来を考えるとき、そこには無視できない3つの大きな流れがあります。それは、業界が直面している課題である「影」の部分と、新たな可能性である「光」の部分の両方を含んでいます。
避けられない現実:新築住宅市場の縮小という「影」
まず、業界が向き合わなければならない現実として、新築住宅の市場が少しずつ小さくなっていることが挙げられます。これは、日本の人口が減り始めていることを考えれば、自然な流れとも言えます。新しい家を建てる数が減れば、そこに取り付けられる建具の数も当然、影響を受けます。
これまでと同じように、新しい建物の仕事だけに頼っていると、仕事の取り合いが激しくなったり、会社の経営が不安定になったりする可能性は否定できません。これが、業界の将来を不安視する声が上がる、一番の理由と言えるでしょう。この「影」の部分から目をそらさず、きちんと認識しておくことはとても大切です。
新たな主役:リフォーム市場の拡大がもたらす「光」
一方で、非常に明るい「光」も見えています。それが、既存の住宅を改修するリフォームやリノベーション市場の大きな広がりです。人々が家で過ごす時間への関心が高まり、「今の住まいをもっと良くしたい」という想いが、この市場を力強く支えています。
特に、国全体で省エネへの意識が高まっていることは、建具業界にとって大きな追い風です。エネルギーの多くが窓やドアから逃げていくことが知られるようになり、断熱性能の高い製品に交換する工事の需要は、年々高まっています。これは、ただ古いものを新しくするだけでなく、「暮らしの質を高める」という新しい価値を提供する仕事であり、業界の新たな主役となりつつある分野です。
未来への変化:暮らしの質を高める「高付加価値」へのシフト
そしてもう一つ、未来に向けた大きな変化が「高付加価値」へのシフトです。これは、建具が単なる「仕切り」ではなく、私たちの暮らしを豊かにする特別な機能を持つ製品へと進化していることを意味します。
例えば、頻発する自然災害に備えて、火災の延焼を防ぐ防火性能や、地震の揺れに耐える頑丈な建具の重要性は増すばかりです。また、在宅で仕事をする人が増えれば、静かな環境を確保するための遮音性能も求められます。このように、お客様一人ひとりの悩みや願いに応える「付加価値」を持った建具が、これからのスタンダードになっていくでしょう。この流れは、建具の仕事が「ただ取り付ける作業」から、「お客様の課題を解決する提案」へと変わってきていることを示しています。
「ただ作れる」だけでは生き残れない。5年後に市場価値が上がる技術者とは?
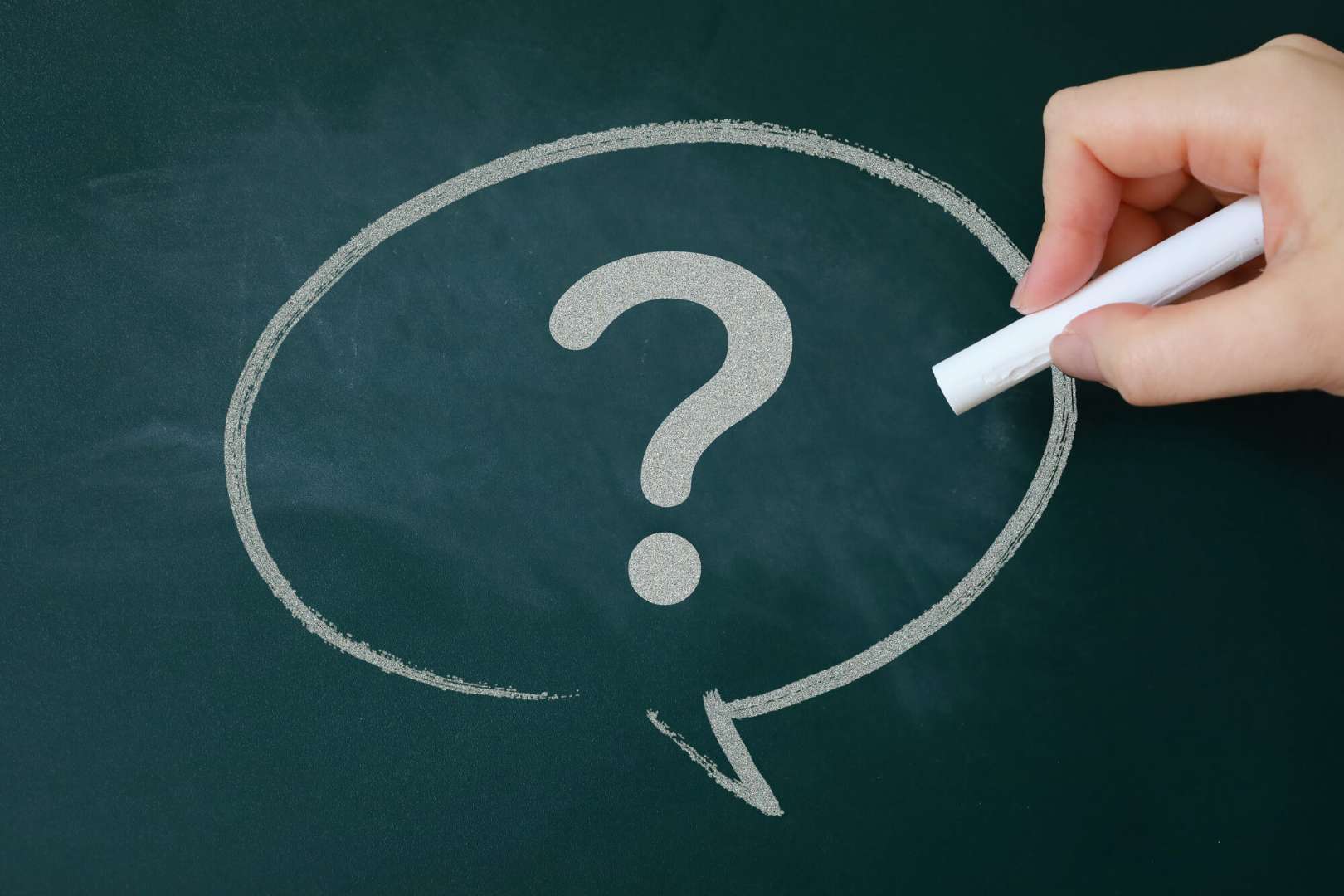
業界を取り巻く環境が変わる中で、そこで働く技術者に求められる力もまた、変化しています。昔ながらの「腕一本」という世界ももちろん大切ですが、それだけでは5年後、10年後に本当に必要とされる人材であり続けるのは難しいかもしれません。これからの時代に市場価値が高まる技術者には、共通するいくつかの特徴があります。
求められるのは「聞き出す力」と「提案する力」
これからの建具の仕事は、「言われたものを、言われた通りに取り付ける」だけで終わりません。お客様が本当に困っていることは何か、どんな暮らしを望んでいるのかを、会話の中から丁寧に「聞き出す力」が何よりも重要になります。
例えば、「冬場、廊下が寒くてつらいんです」という相談を受けたとします。その悩みに対して、「それなら、この断熱性能が高いドアがいいですよ。すきま風も防げるので、暖房の効きも良くなります」といったように、専門家として最適な解決策を「提案する力」。これが、お客様からの信頼に繋がり、「あなたにお願いしたい」と言われる理由になります。技術はもちろんのこと、暮らしに寄り添うパートナーとしての役割が、ますます求められていくでしょう。
デジタル技術は、もはや他人事ではない
「職人の世界だから、パソコンは苦手で…」と感じる方もいるかもしれませんが、建設業界全体でデジタル技術の活用は急速に進んでいます。難しく考える必要はありません。例えば、これまで紙だった図面をパソコンで管理したり、建物の情報を立体的なデータで扱ったりすることが、少しずつ当たり前になってきています。
こうしたデジタルツールを使いこなせることは、これからの技術者にとって、間違いなく大きな強みになります。作業の効率が上がりますし、他の職人さんとの情報共有もスムーズになります。特に、未経験からこの業界に飛び込む方にとっては、経験豊富な先輩たちとの差を埋めるチャンスにもなります。学ぶ意欲さえあれば、新しい時代の武器を手にすることができるのです。
自分の仕事の「前後」を理解する視点
建具の取り付けは、家づくりの工程の一部です。その前には壁を作る大工さんがいて、後には内装を仕上げる職人さんがいます。自分の仕事だけを見るのではなく、その「前」と「後」の工程を理解し、関心を持つ視点が非常に大切です。
全体の流れが分かっていると、「次の人が作業しやすいように、ここまで準備しておこう」といった配慮ができ、現場全体の仕事がスムーズに進みます。時には、建具以外のちょっとした作業を手伝えるような、幅広い知識と技術を持つ人は、どんな現場でも頼りにされる存在です。自分の専門性を深めつつも、周りを見渡せる視野の広さが、あなたの価値をさらに高めてくれるはずです。
【重要】将来性のある企業を見極める「3つのチェックポイント」

業界の未来が明るいとしても、どの会社で働くかはあなたのキャリアにとって非常に重要です。変化の時代に成長し続け、働く人を大切にする。そんな将来性のある優良企業には、いくつかの共通点があります。ここでは、会社選びで失敗しないための「3つのチェックポイント」をご紹介します。
人を「育てる」仕組みと文化があるか
特に未経験から挑戦する場合、これが最も大切なポイントかもしれません。良い会社は、社員を単なる「労働力」ではなく、未来を共に創る「財産」だと考えています。だからこそ、人を育てることにお金と時間を惜しみません。
例えば、信頼できる会社では、入社後にしっかりとした研修期間を設け、道具の名前や安全ルールといった基本の「き」から教えてくれます。また、仕事に必要な資格を取るための費用を会社が応援してくれたり、試験前に勉強会を開いてくれたりする制度が整っていることも多いです。何より大切なのは、先輩たちが後輩の質問に面倒くさがらずに答え、丁寧に技術を教えてくれるような温かい文化があるかどうか。会社のウェブサイトや面接の場で、社員を大切に育てようという姿勢が感じられるか、じっくりと見極めてみてください。
新しい技術や変化に対して前向きか
時代の流れから目を背けず、常に新しいことに挑戦しようという姿勢も、成長する企業の大きな特徴です。昔ながらのやり方に固執せず、より良い方法を模索し続ける会社は、これからも生き残っていける可能性が高いでしょう。
例えば、現場の情報を共有するためにスマートフォンのアプリを導入していたり、作業の負担を減らすために新しい工具や機械を積極的に取り入れていたり。こうした一つひとつの取り組みは、会社の「変化に対する前向きさ」の表れです。そうした環境は、働く側にとっても、常に新しいスキルを身につける機会に恵まれるという大きなメリットがあります。現状維持ではなく、常に一歩先を目指している。そんな雰囲気があるかどうかも、大切な判断基準になります。
仕事の幅が広く、経営が安定しているか
会社の安定性を見極めるには、どのような仕事を手がけているかを確認するのが有効です。もし、特定の取引先や、新築住宅の仕事だけに依存していると、その取引先の状況や景気の波に経営が大きく左右されてしまいます。
一方で、多くの優良な企業では、新築のマンションから、個人住宅のリフォーム、学校や病院といった公共施設の改修工事まで、非常に幅広い現場を手がけています。仕事の種類や取引先の数が多ければ、どこかの仕事が減っても他の仕事でカバーできるため、経営が安定しやすいのです。また、働く側にとっても、様々な現場を経験できることは、技術者としての引き出しを増やし、大きな成長に繋がるはずです。
未経験からでも大丈夫。建具業界で描ける具体的なキャリアステップ
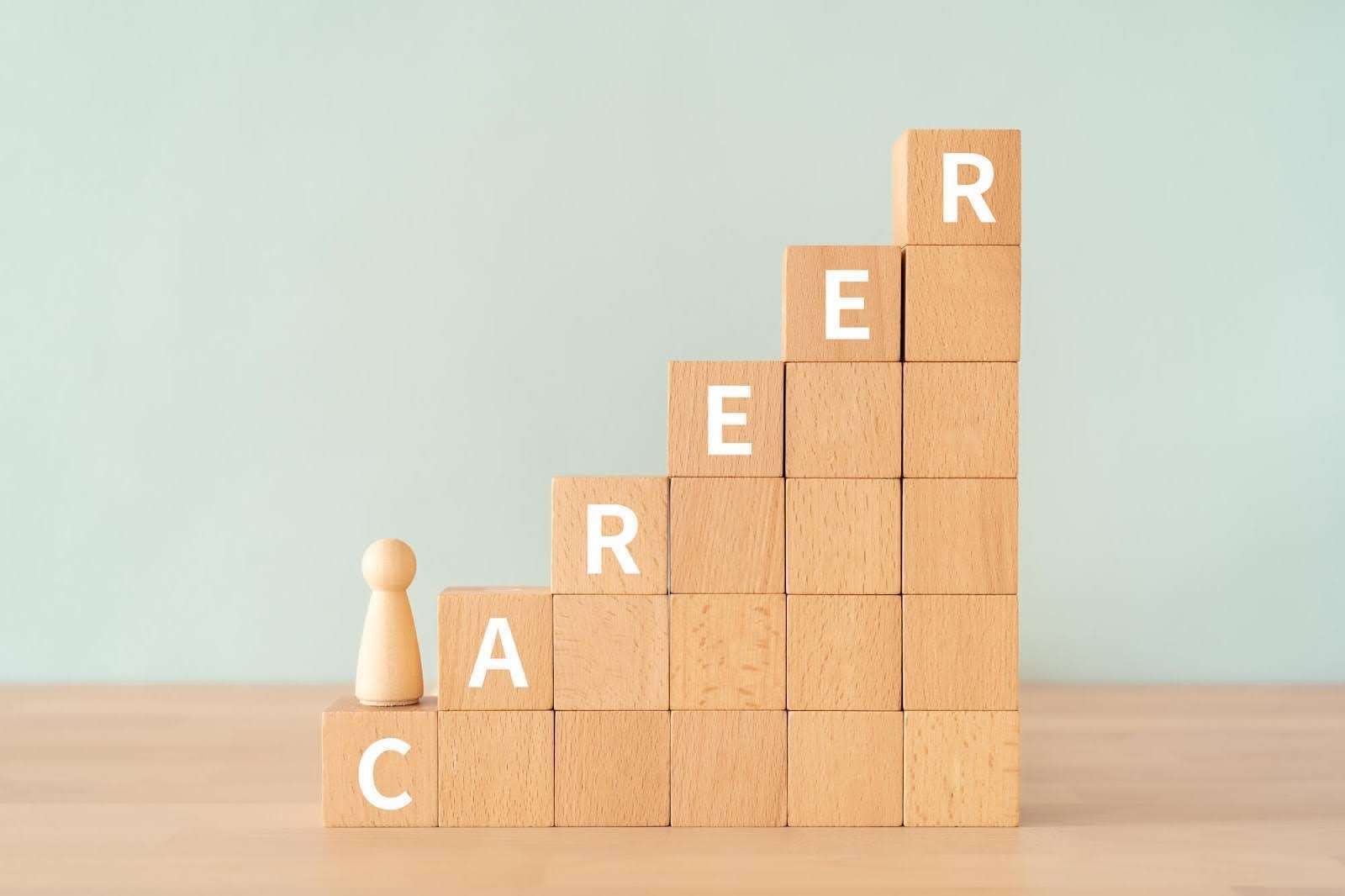
「未経験の自分でも、本当にやっていけるだろうか」という不安は、当然のことだと思います。しかし、しっかりとした会社を選び、一歩ずつ着実に進んでいけば、専門的な技術を身につけ、頼られるプロフェッショナルへと成長していくことができます。ここでは、具体的なキャリアの道のりを描いてみましょう。
未経験から始める人のためのキャリアロードマップ
最初は誰でも初心者です。多くの場合は、先輩職人の補助をするアシスタント業務からキャリアが始まります。まずは、現場の空気に慣れること。そして、道具の名前や使い方を一つひとつ確実に覚え、先輩の指示を正確に理解すること。こうした地道な積み重ねが、すべての土台となります。
個人差はありますが、一つの目安として、1年後には基本的な作業を一人でこなせるようになり、3年も経てば、小さな現場なら責任者として任せてもらえるレベルに到達することも可能です。そして5年後には、現場をまとめる「職長」として後輩を指導する立場になっているかもしれません。大切なのは、焦らず、昨日より今日、今日より明日と、自分自身の成長を信じて続けることです。その真面目な姿勢を、周りは必ず見てくれています。
経験を活かして、さらに高みを目指す道
もしあなたが、建具以外の建設業界での経験をお持ちなら、その知識は大きな強みになります。図面が読めること、現場の段取りがわかること、他の職種の人たちとの連携の仕方を知っていること。それらは、新しい環境でもすぐに活かすことができる貴重な財産です。
その上で、建具のプロとしてさらに高みを目指す道も拓けています。例えば、「建具製作技能士」といった国家資格の取得は、あなたの技術を客観的に証明する大きな武器になります。お客様からの信頼が増すだけでなく、会社によっては資格手当などで給与面でも評価されるでしょう。また、現場経験を積んだ先には、職人として技術を極めるだけでなく、現場全体を管理する「施工管理」へと進むキャリアもあります。より大きな視点からプロジェクトを動かしていく、また違ったやりがいが見つかるはずです。
会社が社員一人ひとりの成長をどう考え、どんな働き方をサポートしてくれるのか。具体的な姿を知ることも、あなたの未来を描く上で大切な一歩になります。
働く環境や、先輩たちの声を見てみる
https://www.kanekokenso.jp/workstyle
まとめ:変化の時代こそ、建具業界は「個の力」が活きる場所になる
ここまで、建具業界の現状と未来、そしてそこで活躍するために必要なことについてお話してきました。
「建具業界はやめとけ」という言葉は、もしかしたら、新築住宅が減っているという一面だけを切り取った意見なのかもしれません。しかし、実際にはリフォーム需要の増加や、より高機能な建具へのシフトといった、大きな成長の可能性が広がっています。
そして、そんな変化の時代だからこそ、求められるのは、ただ言われたことをこなす力ではありません。お客様の悩みに耳を傾ける力、新しい技術を学ぶ意欲、そして周りと協力して仕事を進める姿勢です。こうした「個の力」を磨いていけば、たとえ未経験からのスタートであっても、業界にとってなくてはならない存在へと成長していけるはずです。
自分の手で、人々の暮らしの安全や快適さを形にしていく。時には大変なこともありますが、それ以上に大きな達成感と誇りを感じられるのが、この仕事の魅力です。
この記事が、あなたの未来を考える上で、何か少しでもお役に立てたのなら、これほど嬉しいことはありません。最終的にどのような道を選ぶのか、その判断の主役は、もちろんあなた自身です。
もし、もう少しだけこの仕事のこと、業界のことについて知りたい、心の中にある小さな疑問を解消したいと感じたら、気軽に声をかけてみてください。
お問い合わせはこちらから


